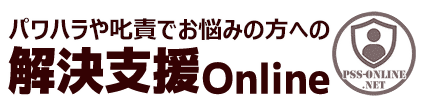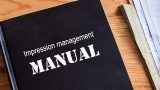態度による「ラベリング」でデキの悪い奴が作り上げられる
パワハラ加害者は、よく被害者にする相手には不機嫌そうな態度で接することがあります。何もしていないのに、話しかけるときに既に怒ってるかのような態度や口調の時すらあります。
そこから、明らかに端から「デキの悪い奴」と決めてかかっていることが見て取れます。言葉でそうは言っていなくとも、態度で一方的にレッテルを貼っているのです。これは一種の「ラベリング」という行為にあたります。
加害者タイプは往々にして差別的な傾向があります。立場が上の人間や好感を持っている相手には愛想よく接する一方、そうではない相手には無感情か不機嫌そうに接する人が少なくありません。社内で誰にでも平等に接する人がいれば、その人と態度を比べてみてください。すぐに納得できると思います。
加害者タイプは、躊躇なく思ったことを態度にも言動にも出す人がほとんどです。しかも、大体、声が大きいので、「みなさん、こいつはデキが悪い社員です」と社内にアピールしているのと同じことになるのです。
そのように、このタイプに悪い印象を持たれると、デキの悪い社員に仕立て上げられてしまいます。平等な態度で接する人だけであれば、特に劣っているわけでもなく他の社員と一緒なのが、実に恐ろしいことです。
同意する態度を取らないようにする
そして、その勝手な決めつけに対し、平身低頭で萎縮しすぎる態度で返してしまう人がいます。そのような弱い態度は、予想を裏切らない(期待通りと言ってもよい)結果を返してしまうことになります。つまり、そのレッテルに対して認めるのと同じ結果を返すことになるのです。(これにより、相手は勝手な決めつけに対して疑いを持たなくなります。また、たまたまミスを犯しただけでも「ほら、また間違えた」と自分の認識の確信を深めます。このような過程を社会心理学では「予測の自己実現」といいます)
また、悪いレッテルを貼られ続けた人も前述したラベリング理論によって、「自分は能力が低い」という思い込みをするようになり、実際に悪い方向へ行ってしまうこともあります。そう考えると、パワハラタイプの人間は、怒ったり注意をしながらもレッテル貼りやラベリングによって自分でわざわざデキない社員を作っていることになるのです。何と愚かなことでしょうか。
これをよく理解して、その罠に嵌められないようにしなければなりません。
前述した通り、相手の期待通りの態度を返すことは、それを認めることになります。まず、絶対に芯の強い態度を貫き通すことが必要です。(但し、反抗的だとか開き直りと捉えられないように注意してください)弱い態度を抑え、強い態度を表出することは、当サイトで勧めているPSS対処法™でも基本的なことです。
特に注意を要するのは、すぐに謝ってしまう人です。間違いを犯したのであれば謝っても良いですが(それでも過度に萎縮した態度は取らない方が無難です)、そうではないのに何か指摘をされた程度で簡単に「すみません、すみません」とコメツキバッタのようにペコペコしてしまう人がいます。これでは、ラベリングはますます強力になるだけです。
流れを逆転させられれば善循環に持っていける
加害者は相手の印象によって態度が違うと言いましたが、これは考えようによってはうまく利用することもできます。
相手の印象によって態度を変えやすい人間は、逆にデキると思っている相手にもやはり「デキる人」という態度で接しています。そのような態度は相手にも伝わり、それによって実際にその期待通りの人になっていきやすくなります。(これは「ピグマリオン効果」と呼ばれる効果です)
つまり、デキないと思われると「ラベリング」と「予測の自己実現によ」って悪循環を作り上げられてしまう危険性がある一方、デキるという印象の刷り込みを行っていけば、やはり同様の効果でそう思い込ませやすいということです。そして、「ピグマリオン効果」によって善循環にすることもできます。
実際、流れを逆転させることに成功するととても楽になります。(先ほどの例とは逆で、社内でデキる社員というPRも行ってくれます)これは私が幾度も経験していることです。PSS対処法™を使ってその流れを逆転させたことは言うまでもありません。